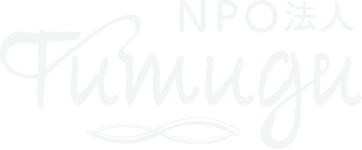未来の子どもたちの為の
Tumugu
サポーター制度

我々の活動に賛同してくださる方を募集しています。
NPO法人Tumuguは未来ある子ども達の児童養護ファミリーホームの建設を2030年に予定しています。サポーター年会費は50%をサポーター特典・運営・事務費、50%を施設建設・運営資金として使用致します。生まれ育った環境によって家庭を知らない子ども達へ、志ある方のサポートを募集しています。
Tumugu一般サポーター
料金
6,000円/年 (月額500円)
年1回の口座引落し
特典
各セミナー等案内、年3回の会報誌、 行事への特別案内
Tumugu法人サポーター
料金
12,000円/年 (月額1,000円)
年1回の口座引落し
特典
各セミナー等案内、年3回の会報誌
会報誌へ企業紹介掲載、行事への特別案内
エンディングサポーター
料金
8,000円/年
特典
1.エンディングノート 2.パワポ 1.2.3 講座分 3.いつでもエンディング講座再受講 4.エンディングサポーター協力体制 5.エンディングサポーター講座再受講 6.いつでも相談→LINE・メール・電話 7.パワポ編集のお手伝い 8.パソコン貸出 取りに来られる方のみ(受講日前日~当日~翌日 計 3 日間貸出) 9.講座開講スペースの貸出
ホームDEナースサポーター
料金
10,000円/年
Tumuguの未来
- ホームDEナース(専属看護師)
- 児童養護ファミリーホーム
- みんなでつくる空き家バンクの児童養護ファミリーホーム
- つむぐ電話
(子育て世代お母さんのサポート×独居の方のサポート) - 認知症喫茶
(介護度の低い方が気軽に来てお茶をしながら健康管理) - ファミリーつむぐの家
(産後里帰りが出来ない人、ひとり親、独居のご老人など) - アニマルセラピー
- アロマテラピー
- 家でできる結婚式(人生で自分の為に人が集まるのは生まれたとき・結婚式・お葬式)
- つむぐの畑
(まだまだワシは現役じゃ) - つむぐ食堂
(つむぐ畑のお野菜でお惣菜を) - 子どもの居場所(幼稚園生・小学生が安心して帰れる場所(急な発熱のお迎えも出来るといな・・・))
ファミリーホームについて
-
ファミリーホームって
どんな場所?ファミリーホームを説明する時に「里親を少し大きくしたもの」と表現されることがあります。
里親の場合、子どもを養育できるのは最大 4 人までですが、ファミリーホームの場合は 6 人まで養育が可能です。
したがって、ファミリーホームには「施設」と「里親」両方の側面があります。
実親さんによっては「里親に預けると子どもがそのままとられてしまうのではないか」と心配され、里親家庭に子どもを預けるのを躊躇されるケースもあります。
しかしファミリーホームですと「施設」としてのイメージもあるため、実親さんが安心して預けられる場合もあるようです。
-
ファミリーホームが
期待されていること「社会的養護の課題と将来像」では、ファミリーホームについても、里親支援と同様の支援体制の中で支援を
推進することが必要とされています。ファミリーホームの今後の課題として、①大幅な整備促進②専門性の向上と支援体制の構築という2つのことが挙げられています
-
ファミリーホームに
なるための基準とはファミリーホームが制度として事業化されたのは、平成21年度からです。ファミリーホームは厚生労働省の管轄で「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱」に準じます。
第7 職員
- (1)ファミリーホームには、2人の養育者及び1人以上の補助者(養育者が行う養育について養育者を補助する者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。なお、この2人の養育者は一の家族を構成しているもの(夫婦であるもの)とする。
- (2)(1)の定めにかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保される場合には、当該ファミリーホームに置くべき者を、1人の養育者及び2人以上の補助者とすることができる。
- (3)養育者は、当該ファミリーホームに生活の本拠を置く者でなければならない。
- (4)養育者は、次の①から④までのいずれか及び⑤に該当する者をもって充てるものとする。補助者は、⑤に該当する者とする。
- ① 養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する者
- ② 養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する者
- ③ 児童養護施設等において児童の養育に3年以上従事した者
- ④ ①から③までに準ずる者として、都道府県知事が適当と認めた者
- ⑤ 法第34条の20第1項各号の規定に該当しない者
- (5)養育者及び補助者は、家庭養護の担い手として里親に準じ、児童福祉法施行規則第1条の34及び第1条の37第2号に定める研修を受講し、その養育の質の向上を図るよう努めなければならない。